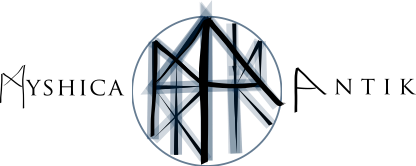6月18日(日)大江戸骨董市 09:00-15:00
-

アンティークバンド織機、スウェーデン
¥50
SOLD OUT
スウェーデン19世紀のバンド織機。 ■国:スウェーデン ■年代:19世紀 ■サイズ:約 高 34.5cm 横 76㎝ 底面 奥行 27㎝ ■状態:時間の傷がいい味をだしている。
-

Knud Kühn(クヌート・キューン、1880-1969) 花瓶 20世紀初
¥50
SOLD OUT
Knud Kühn(クヌート・キューン、1880-1969)は、デンマークの陶芸家です。彼は、デンマークの伝統的な陶芸を復興させ、現代的な陶芸の分野で先駆的な役割を果たしました。彼の作品は、シンプルで洗練されたデザインが特徴で、世界中の美術館に収蔵されています。 Knud Kühnは1880年にデンマークのオーデンセで生まれました。彼は1900年にコペンハーゲンの王立芸術アカデミーで陶芸を学びました。卒業後、デンマーク各地で陶芸を教えました。1919年に自身の陶芸工房を設立し、1969年に亡くなるまでそこで制作を続けました。 Knud Kühnの作品は、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。彼は、デンマークの伝統的な陶芸の要素を現代的なデザインに取り入れました。彼の作品は、世界中の美術館に収蔵されています。 ■国:デンマーク ■作家:Knud Kühn(クヌート・キューン、1880-1969) ■年代:20世紀頭。 ■サイズ:約 高 14cm Φ15cm Φ下6.9㎝ 口部分内寸 Φ8.7cm ■状態:
-

【北欧アンティーク】スウェーデン 18-19世紀木製皿 (Trätallrik) - 素朴な暮らしの民藝品
¥50
SOLD OUT
スウェーデンの長い歴史の中で育まれた、温もりあふれる木工品をご紹介します。こちらは18世紀から19世紀にかけて、スウェーデンの家庭で日常的に使われていたと考えられている、アンティークの木製皿、通称「Trätallrik(トレタッルリク)」です。 伝統の技と厳選された素材 この皿は、主にスウェーデン南西部のセーハラッドスビーグデン地方(Sjuhäradsbygden)「rödbok」(ロッドボーク)と呼ばれるヨーロパブナ材(赤ブナ) を用いて作られました。赤ブナは、密度が高く丈夫で、食材の風味を損なわない特性を持つため、食器に適していました。この皿は、足踏み式の轆轤、「svegsvarv(スヴェグスヴァルヴ)」を用いて、熟練した職人によって丁寧に挽かれています。生木を削ることで、滑らかで美しい表面に仕上げられており、手仕事ならではの温かみが感じられます。木材の持つ自然な木目や風合いがそのまま活かされた素朴な表情が最大の魅力です。 歴史に刻まれた日常の道具 木製の皿や鉢は、スウェーデンでは中世末期には登場していましたが 、18世紀に入ると農民の家庭で一般的になりました 。この皿の直径は約18.5cmから19cmと、当時の赤ブナ材の木製皿の典型的なサイズである19-20cmに近く、まさに当時の食卓で、日々食事が盛られていたであろう実用的なサイズ感です。 セーハラッドスビーグデン地方の行商人、「gårdfarihandlarna(ゴードファリハンドラルナ)」あるいは「skålaknallarna(スコーラカナラルナ)」は、17世紀から19世紀半ばにかけて、このような挽き物(木工旋盤で作られた品物)をスウェーデン各地や近隣国に大量に運び、広く流通させました 。彼らが運んだ品物の中には、年間数十万枚もの木製皿が含まれていました。 当時の農家では、普段の食事は共同の鉢から直接食べていたという記録もありますが、このサイズの皿は特別な集まり("gillen")だけでなく、日常の食事でも個人用の皿として使われることが増えていったと考えられています 。多くの皿には、所有者を示すイニシャルや家紋("bomärke")が刻まれ、識別のために使われました。この皿にも二つの印はあります。木製皿は19世紀後半から20世紀初頭にかけて徐々に使われなくなり、現代では貴重なアンティーク品、古民藝として高い価値を持っています。 手仕事の温もり、時を経た木肌の深い味わい、そして北欧の素朴な暮らしに思いを馳せることのできる、貴重な一品です。お部屋のディスプレイや、テーブルコーディネートのアクセントとしていかがでしょうか。 •国: スウェーデン •年代: 18-19世紀 •サイズ: 約 Φ18.5cmから19cm •素材: ヨーロパブナ材(赤ブナ "rödbok") •状態: 経年による傷、シミ、歪みなどが見られますが、アンティークの風合いとしてお楽しみいただけます。
-

アカンサス彫刻の木製スプーン&フォーク(ノルウェー / 19世紀末〜20世紀初頭)
¥50
SOLD OUT
北欧の豊かな自然と、脈々と受け継がれる職人技が息づく、大変貴重なノルウェーのフォークアート(民藝)作品です。 古典的な装飾モチーフであり、ノルウェーの木彫工芸でも特に愛されてきた**アカンサス(ハアザミ)**の文様が、柄の全体にわたり、流麗かつダイナリーに彫り込まれています。持ち手の曲線美と相まって、手に取るたびに温もりと芸術性を感じさせます。 長年使い込まれたことで得られた木肌の深い色合いと滑らかな質感が、このカトラリーに豊かな歴史を物語っています。 様式: ノルウェーの伝統的な木彫フォークアート(アカンサス様式) 年代: 19世紀末〜20世紀初頭頃 素材: 木 サイズ: スプーン: 全長 約32.4 cm / 最広部 約5.8 cm フォーク: 全長 約32.4 cm / 最広部 約3.9 cm 飾りとしての存在感はもちろん、ノルウェーの木彫芸術の歴史を感じさせるコレクターズアイテムとしても魅力的な一品です。ご自宅のインテリアに、あるいは特別な方への贈り物にいかがでしょうか。
-

北欧アンティーク】スウェーデン 18-19世紀 手彫り木製ボウル - 素朴な暮らしの民藝品(鉄補修あり)
¥50
SOLD OUT
スウェーデンの豊かな森から生まれた、素朴で力強い木製ボウルをご紹介します。こちらは18世紀から19世紀にかけて、スウェーデンの農家で日常的に使われていたと考えられている、アンティークの手彫り木製ボウルです。年月を経て刻まれた木肌の表情からは、当時の人々の暮らしが伝わってきます。 北欧の自然と伝統の技 このボウルは、主にスウェーデン南西部のセーハラッドスビーグデン地方(Sjuhäradsbygden)を含む地域で、耐久性があり食材の風味を損ないにくいヨーロパブナ材(赤ブナ "rödbok")を用いて作られたと考えられます。このボウルは、轆轤で挽かれた皿や一部のボウルとは異なり、木材の塊から丁寧に彫り出して 形作られています。手仕事ならではの温かみと、一点ごとに異なる木目や風合いが魅力です。 歴史に深く根差した日常の道具 木製のボウルや皿は、18世紀頃からスウェーデンの農村部で広く使われるようになりました。この時代の農家では、19世紀後半頃までお粥(gröt)や汁物などの普段の食事を、大きな共同の鉢から家族みんなで食べる という習慣が一般的でした。 このボウルのサイズ、長さ約28.5cm、幅約17.6cm、高さ約7~7.7cmは、まさにこのような共同での食事や、あるいはパン生地をこねたり発酵させたりするための実用的な「生地ボウル(パン生地を入れるためのボウル)として、当時の暮らしに根差していたことを示しています。セーハラッドスビーグデン地方の行商人「skålaknallarna(スコーラカナラルナ)」たちは 17世紀から19世紀半ばにかけて、このような木製の挽き物や彫り物を大量に作り、スウェーデン各地や近隣国に運び販売することで、これらの道具を広く普及させました。 年月を物語る風合いと補修跡 このボウルは長い年月を経て、使い込まれた道具だけが持つ独特の深い色合いと風合いをまとっています。表面には経年による使用感や傷が見られますが、それもまた歴史の証であり、古民具としての魅力となっています。 特筆すべきは、側面に確認できる鉄の糸による古い補修跡です。これは、かつてこのボウルが割れてしまった際に、当時の持ち主が大切に使い続けるために施した、伝統的な修繕の痕跡です。このような手仕事による補修跡は、現代の大量生産品にはない、一つ一つの道具が丁寧に扱われていた時代の物語を伝えてくれるものです。割れても捨てずに直して使い続けた、物を大切にする北欧の人々の精神性をも感じさせます。 北欧の素朴な民藝品として、空間に温かみを添えるディスプレイに。また、歴史を物語る古民具として、当時の人々の暮らしに思いを馳せるきっかけとなるでしょう。 • 国: スウェーデン • 年代: 18-19世紀 • サイズ: 約 長さ28.5cm, 幅17.6cm, 高さ7~7.7cm • 素材: ヨーロパブナ材(赤ブナ "rödbok") • 状態: 経年による傷、シミ、木材の収縮によるヒビなどが見られますが、アンティークの風合いとしてお楽しみいただけます。鉄の糸による古い補修跡があります。
-

19世紀スウェーデンレッドウェアボウル
¥50
SOLD OUT
北欧の力強いフォークアートが感じられる、19世紀スウェーデン製の赤土陶器ボウルです。 赤茶色の素朴な土の質感を活かし、外側には黒いスリップ(化粧土)で描かれた生命力溢れる植物や葉っぱのような文様が、一つ一つ丁寧にスタンプされたかのように施されています。この手仕事の温かさと、力強い筆致が、見る者の心を惹きつけます。 内側には深みのある飴色の釉薬がかけられており、外側の素朴なデザインとのコントラストが美しいです。縁には濃い茶色の釉薬が施され、全体を引き締めています。 このボウルは、スープやシリアル、サラダボウルとして日常使いしやすいサイズ感です。また、存在感のあるデザインは、キッチンやダイニングに飾るオブジェとしても魅力的です。 100年以上前の時を経てもなお、現代の暮らしに温もりと個性を与えてくれる、特別なアンティークボウル。北欧のフォークアートや手仕事がお好きな方に、ぜひおすすめしたい逸品です。 ■国:スウェーデン ■年代:19世紀 ■サイズ:約 Φ 19.8-20cm 高さ7.9-8.2cm ■素材:陶器 レッドウェア ■状態: 経年による風合いや貫入、釉薬の剥がれなどが見られます。歴史を物語る味わい深いコンディションです
-

印付きスウェーデン19世紀のスヴェープアスク
¥50
SOLD OUT
19世紀スウェーデンの伝統的なスヴェパスク(Svepask)です。 薄く削った木の板を曲げて成形し、樺の根の皮で縫い留めた、北欧らしい素朴で温かな手仕事が感じられる逸品。 本来はパンや乾物、バター、釣り道具などの収納に用いられ、日々の暮らしを支えてきました。 木肌の経年変化や針穴の風合いが、長い時を経た静かな物語を語りかけてくれます。 ■国:スウェーデン ■年代:19世紀 ■サイズ:約 高さ10.5cm 横幅19.1cm 奥行12.5cm ■素材:木、樺の根皮
-

19世紀スウェーデンのスヴェ
¥50
SOLD OUT
こちらは、19世紀のスウェーデンで作られた、素朴な魅力あふれるスヴェープアスク(Svepask)です。Svepaskは、木を薄く削り、熱湯で曲げて作られる、北欧に古くから伝わる伝統的な木工品です。 経年により飴色に変化した木肌は、温かみのある風合いを醸し出しています。蓋には焼印で施された飾り模様があり、手仕事ならではの愛らしさが感じられます。本体を留めるステッチのような木製の留め方も、美しいデザインのアクセントになっています。 もともとは例えばバター、スパイスや小物を入れるために使われていましたが、現在は裁縫道具やアクセサリー、大切な手紙などを入れる宝物箱としてお使いいただけます。どのような場所にも馴染みやすいデザインですので、お部屋のインテリアとしてもおすすめです。 年月を経たからこそ生まれる、深みのある佇まいをお楽しみください。 ■国:スウェーデン ■年代:19世紀 ■サイズ:約 高さ7.5cm 横幅16.1cm 奥行 8.4cm ■素材:木材、白樺の根っ子 ■状態:経年によるキズや擦れ、汚れはあります
-

カール・ハリー・スタルハン作 ロールストランド ストーンウェア(炻器)の小さな器 - 優雅な日本の美意識が息づく北欧ヴィンテージ
¥50
SOLD OUT
この度ご紹介するのは、スウェーデンの名窯ロールストランド社で、陶芸家カール・ハリー・スタルハン(Carl-Harry Stålhane, 1920-1990)によって1942年に製作された、ストーンウェア(炻器)の小さな器です。これは、北欧デザインの黎明期における彼の芸術性を象徴する逸品であり、日々の暮らしに静かな存在感を放ちます。 ロールストランドは、1726年に創業したスウェーデン最古の陶磁器メーカーの一つであり、ヨーロッパでも有数の歴史を誇ります。スウェーデン王室御用達としてその地位を確立し、初期の磁器生産から時代とともに素材とデザインの変遷を経て、常に陶磁器産業のパイオニアであり続けました。 カール・ハリー・スタルハンは、20世紀スウェーデン陶磁器界において国際的に高く評価された主要な陶芸家であり、スウェーデン陶芸芸術の偉大な名の一つとされています。彼は1939年に19歳でロールストランド社に入社し、装飾画家としてそのキャリアを開始しました。当初は表現主義の画家イサーク・グリューネヴァルト(Isaac Grünewald)の指導を受け、後に両者は共同制作を行い、その陶磁器はスウェーデン国立美術館で展示されるほどの成功を収めました。彼は一時、ストックホルムのグリューネヴァルト美術学校(1943-1946年または1944-1946年)やパリのアカデミー・コラロッシ(1947-1948年)で絵画と彫刻を学びました。 この作品が制作された1940年代は、スタルハンがロールストランドに在籍して間もないキャリアの初期にあたります。彼は、デンマーク・フィンランドの陶芸家でありデザイナーのグンナー・ニールンド(Gunnar Nylund, 1904-1997)のアシスタントとして、様々な陶磁器の装飾を手がけていました。 スタルハンの初期の作品、特に1940年代から1950年代にかけてのものは、中国の宋代陶磁器の芸術的伝統を取り入れた、優雅で細身の左右対称なフォルムと、単色またはマットな釉薬を特徴としています。これらの繊細でエレガントな炻器の壺は、近年国際的なインテリアで需要が著しく高まっています。 彼の作風は、1960年代に入るとより重厚で粗削りな作品へと変化しますが、本品は1942年に制作されたものであり、彼の初期の洗練された美意識が色濃く反映されています。彼は単なるデザイナーに留まらず、熟練した陶芸家でもあり、全てのユニークな手作りのフォルムを自ら成形し、装飾的なモチーフも手作業で施しました。彼が追求した作品の完璧さと、高度な技術を要する釉薬は、当時の著名な陶芸家であったアンダース・ルーヴァルドをも魅了し、彼がスタルハンの作品を長年収集し、その精巧な釉薬に感嘆するほどでした。 1953年には、重要なミッドセンチュリー陶芸家グンナー・ニールンドの後任として、ロールストランドの芸術監督兼チーフデザイナーに就任し、その名を不動のものとしました。スタルハンは、ロールストランドで40年間にわたるキャリアを楽しみ、1939年から1973年まで同社の主要な芸術家として活動しました。彼は工業生産の食器デザインと、スタジオでの大量の炻器製作、そして公共空間のモニュメンタルな壁面レリーフの両方を手掛け、その功績は現代においても国際的に高く評価されています。彼の作品は、ニューヨーク近代美術館(MoMA)やストックホルム国立美術館など、世界中の著名な博物館に収蔵されています。 本品に宿るスタルハンの手仕事の痕跡と、釉薬が持つ無限の美しさは、まさに彼の芸術性の証です。 • 丸みのある柔らかいフォルムは、日本の伝統的な美意識である「侘び寂び」や「用の美」といった概念と深く共鳴します。素材の質感を活かし、自然な風合いを尊ぶその姿勢は、単なる北欧デザインの枠を超え、日本の文化的な感性にも響く普遍的な価値を宿しています。 • 釉薬のわずかなムラや、底面のざらりとした質感は、炻器の釉薬が焼成時の窯の条件や釉薬の厚みによって一つ一つ異なる表情を見せるため、均一ではない自然なムラや窯変(Kiln variation)唯一無二の美しさは、各作品が持つ独自の個性を際立たせ、「一点物」としての希少性と特別な魅力を生み出しています。 本品は、約 Φ4.7cm 高さ2cmというコンパクトなサイズ感です。小さな花を飾る一輪挿しとして、また、お茶の時間に使う小さな器として、暮らしの中にそっと溶け込むような佇まいです。炻器は高温で焼成されており、耐久性に優れ、日常使いに適しています。 年月を経たからこそ生まれる、深みのある佇まいをお楽しみください。カール・ハリー・スタルハンという20世紀を代表する巨匠の、特にキャリア初期の洗練された時代の作品であり、ロールストランドという歴史あるメーカーの、その芸術的功績を物語る一点です。この出会いを逃す手はありません。 ■国:スウェーデン ■会社:ロールストランド ■作家:カール・ハリー・スタルハン ■製造年代:1942年 ■サイズ:約 Φ4.7㎝ 高さ2㎝ ■素材: ストーンウェア(石器) ■状態:
-

19世紀スウェーデンスヴェープアスク
¥50
SOLD OUT
■国: ■年代: ■サイズ:約 Φ 高さ 横幅 奥行 ■素材: ■状態:
-

【稀少】カール・ハリー・スタルハン作 ロールストランド SVKシリーズ ストーンウェアカップ - 自然の息吹が宿る北欧ヴィンテージ 侘び寂びの美意識が息づく、巨匠スタルハンの手による逸品。
¥50
SOLD OUT
1. はじめに:北欧デザインの粋と普遍的な価値 この度ご紹介するのは、20世紀スウェーデン陶磁器界の巨匠、カール・ハリー・スタルハンがロールストランドのためにデザインしたSVKシリーズのストーンウェアカップです。北欧デザインは、その機能性と芸術性の融合により、世界中で愛され続けていますが、特にスウェーデンの陶磁器は、その中でも独自の地位を確立しています。本製品は、まさに「用の美」を体現する逸品であり、日々の暮らしに溶け込みながらも、空間に静かな存在感を放ちます。 このストーンウェアカップが持つ美学は、日本の伝統的な美意識である「侘び寂び」や「用の美」といった概念と深く共鳴します。素材の質感を活かし、自然な風合いを尊ぶその姿勢は、単なる北欧デザインの枠を超え、日本の文化的な感性にも響く普遍的な価値を宿しています。この共鳴は、製品が単なる日用品ではなく、精神性や哲学を内包する特別な存在として、日本の消費者に深く訴えかけることでしょう。北欧のアンティーク民芸品や北欧ヴィンテージ工芸品の愛好家の方々に、特にご注目いただきたい一品です。 2. デザイナー:カール・ハリー・スタルハン - 陶磁器界の巨匠の軌跡 カール・ハリー・スタルハン (1920-1990) は、20世紀スウェーデン陶磁器界において、最も影響力のあるデザイナーの一人としてその名を刻んでいます。彼は国際的に高い評価を受け、そのユニークな手作りストーンウェアと産業用食器で知られています。 スタルハンは1920年にスウェーデンのマリ―スタッドで生まれました。1939年、19歳でスウェーデンの名門陶磁器メーカー、ロールストランドに入社し、装飾画家としてキャリアをスタートさせました。初期には表現主義の画家アイザック・グリューネヴァルトの指導を受け、後に彼と共同で制作を行い、その成功によりスウェーデン国立美術館での展示に招待されました。 1943年から1946年にはストックホルムのグリューネヴァルト美術学校で絵画と彫刻を学び、さらに1947年から1948年にはパリのアカデミー・コラロシで彫刻を学びました。 30歳になる頃にはマイスター陶芸家となっており、1953年には重要なミッドセンチュリーの陶芸家グンナー・ニュルンドの後任として、ロールストランドのアートディレクター兼チーフデザイナーに任命されました。 スタルハンの初期の作品、特に1940年代から50年代にかけてのものは、中国の宋王朝の陶磁器芸術の伝統を取り入れた、優雅で繊細な対称形のフォルムと、単色またはマットな釉薬が特徴です。この時期の作品には「ハーレファ―(harpäls)」のような艶やかな釉薬も用いられました。 1960年代に入ると、スタルハンの作品は、より重厚で粗削りな、印象的なスケールの作品へと変化しました。彼は異なる地元の粘土や色、釉薬技術を実験し、分厚くかけられた釉薬が特徴となりました。1960年のストックホルムのギャラリー・ブランシェでの新作コレクションでは、「重厚で、原始的で、頑丈で、劇的」と評され、当時の陶磁器の反潮流を象徴するものでした。彼は、自身のユニークな手作りの形をすべて自ら実行し、装飾的なモチーフも手作業で施しました。 1973年、スタルハンはロールストランドを退社し、自身のスタジオ「Designhuset」を設立しました。この時期も陶芸制作を続け、中国や日本の伝統への回帰を深め、独自の土や鉱物からなる釉薬の実験に注力しました。 彼の作品は、ニューヨーク近代美術館 (MoMA)、ストックホルム国立美術館、コペンハーゲン工業美術館、ロンドン Victoria & Albert Museum など、世界中の主要な美術館に所蔵されています。また、1951年にはミラノ・トリエンナーレでゴールドメダル、1954年にはディプロム・ドヌールを受賞するなど、数々の国際的な賞に輝きました。スタルハンは、ヴォルボ本社(イェーテボリ、1967年)やカンザスシティのコマース・トラスト・カンパニーなどの公共作品も手掛けています。 3. 製造元:ロールストランドの歴史と伝統 ロールストランドは、1726年に創業したスウェーデンで最も古い陶磁器メーカーであり、ヨーロッパにおいても有数の歴史を誇ります。スウェーデン王室御用達としてその地位を確立し、初期の磁器生産から時代とともに変化する素材とデザインの変遷を経て、常に陶磁器産業のパイオニアであり続けました。20世紀に入ると、アール・ヌーヴォーからモダニズムへの移行期において、ウィルヘルム・コーゲやグンナー・ニールンドといった著名なデザイナーを招聘し、芸術性と商業性を両立させる戦略で革新を遂げました。 第二次世界大戦後、ロールストランドはよりモダンで機能的なデザインへと舵を切る中で、カール・ハリー・スタルハンを主要なデザイナーとして迎え入れました。スタルハンがロールストランドにもたらしたストーンウェアの技術と芸術性は、同社の製品ラインに新たな息吹を吹き込み、その後の方向性に大きな影響を与えました。伝統的な磁器製造で知られる老舗企業が、スタルハンを起用してストーンウェアという新素材とモダンなデザインに挑戦したことは、単なる製品ラインの追加ではなく、企業としての先進性と適応力の証です。このSVKシリーズのカップは、ロールストランドという歴史ある企業が、いかにしてモダニズムの波に乗り、革新を追求し続けたかを示す具体的な証拠であり、その歴史的な意義が製品の価値をさらに高めています。 4. SVKシリーズ:その特徴と魅力 SVKシリーズは、カール・ハリー・スタルハンが1950年代後半から1960年代にかけて手掛けた、ロールストランドの代表的なストーンウェア作品群の一つです。このシリーズは、自然素材への回帰と手仕事の温かみを重視したスタルハンのデザイン哲学が凝縮されており、その独特な美学で多くのコレクターを魅了してきました。 SVKシリーズの最大の魅力は、ストーンウェアならではの豊かな釉薬の表現にあります。自然なアースカラーを基調とした、半マットな質感の釉薬は、光を柔らかく反射し、表面には微細な斑点、いわゆる「ゴマ塩」のような砂粒状のテクスチャが散りばめられています。これにより、視覚的な深みと触覚的な魅力が加わり、素朴ながらも洗練された温かみが感じられます。ストーンウェアの釉薬は、焼成時の窯の条件や釉薬の厚みによって一つ一つ異なる表情を見せるため、均一ではない自然なムラや窯変が生じます。この「偶然性」から生まれる唯一無二の美しさは、量産品でありながら各カップが持つ独自の個性を際立たせ、「一点物」としての希少性と特別な魅力を生み出し、所有する喜びを深めます。フォルムはシンプルでありながら力強く、安定感のある形状が特徴です。また、控えめながらも印象的な手彫りや型押しによる幾何学的なパターンが施されており、光の当たり方や見る角度によって表情を変える繊細な装飾の妙もSVKシリーズの大きな特徴です。 5. ストーンウェアカップ:詳細な商品解説 このカール・ハリー・スタルハン作SVKシリーズのストーンウェアカップは、そのコンパクトなサイズと洗練されたデザインが融合した、まさに北欧デザインの傑作です。 デザイナー (Designer) カール・ハリー・スタルハン (Carl Harry Stålhane) メーカー (Manufacturer) ロールストランド (Rörstrand) シリーズ (Series) SVK 素材 (Material) ストーンウェア (Stoneware)(石器) 直径 (Diameter) 7.7cm 高さ (Height) 5.1cm 製造年代 (Production Period) 1950年代後半〜1960年代 (Late 1950s - 1960s) 原産国 (Country of Origin) スウェーデン (Sweden) 外観と質感: カップ全体は、温かみのある淡い黄土色からベージュ、あるいはライトグレーがかった色合いで、自然の土の色を思わせる落ち着いたトーンです。釉薬の濃淡により、表面には微細なグラデーションが見られ、単調ではない豊かな表情をしています。半マットな質感の釉薬は光を柔らかく反射し、表面には微細な斑点、まるで砂粒が散りばめられたようなテクスチャが特徴的です。これはストーンウェア特有の素朴さと温かみを強調し、視覚だけでなく触覚にも訴えかける魅力となっています。 カップの胴部の中央から上部にかけては、繊細な幾何学模様が施されています。放射状に広がる線と、それを横切る水平線が組み合わさったような、菱形を連想させるパターンが見て取れます。この模様は釉薬の下に施されたエンボス加工か、あるいは線刻によるものであり、光の当たり方や見る角度によって表情を変え、静かながらも奥行きのある美しさを生み出しています。釉薬のわずかなムラや、手作業によると思われる微細な凹凸が、機械的な均一性とは異なる、一つ一つのカップが持つ個性と温かみを物語っています。 フォルムとサイズ: フォルムは、底に向かって緩やかにすぼまり、口縁部に向かってわずかに広がる、安定感のある逆円錐形(または台形)です。重心が低く設計されており、手に馴染みやすく、実用性にも優れています。直径7.7cm、高さ5.1cmというコンパクトなサイズは、エスプレッソカップや日本茶の湯呑み、あるいは小鉢やデザートカップとしても使用できる汎用性を示唆します。 素材と職人技: 素材は高温で焼成されたストーンウェア(炻器)であり、耐久性に優れ、日常使いに適しています。土の持つ素朴な風合いと、釉薬の豊かな表情が特徴です。このカップには、カール・ハリー・スタルハンの洗練されたデザイン哲学と、ロールストランドの熟練した職人による手作業の融合が息づいています。一つ一つのカップに、デザイナーの意図と職人の確かな技術が込められています。 状態: 本製品はヴィンテージ品であり、製造から年月を経たことによる微細な使用感や経年変化が見られる場合があります。例えば、底面の擦れや、釉薬の貫入(表面のひび割れのように見えるもの)などが挙げられますが、これらは製品が持つ歴史と物語を物語るものとして、その価値を一層高める要素となります。特筆すべき大きな欠けやヒビなどはなく、良好な状態を保っています。このカップは、そのコンパクトなサイズと安定したフォルムにより、実用的な機能美を追求しつつ、ストーンウェア特有の質感と釉薬の表情が、視覚だけでなく触覚にも訴えかける「触れるアート」としての魅力を提供します。単なる鑑賞品ではなく、日常に溶け込むことで真価を発揮する、まさにデザインの典型と言えるでしょう。 6. コレクションとしての価値と推奨される使用シーン このカール・ハリー・スタルハン作SVKシリーズのストーンウェアカップは、単なる器以上の価値を秘めています。まず、カール・ハリー・スタルハンという20世紀を代表する巨匠の作品であること、そしてロールストランドという歴史あるメーカーの、特に歴史的転換期を象徴するSVKシリーズの一員であるという点が、そのコレクターズアイテムとしての価値を不動のものにしています。北欧ヴィンテージ品としての希少性は高く、時間の経過とともにその価値が増す可能性も秘めています。さらに、ストーンウェアの特性により一点一点異なる釉薬の表情は、唯一無二のコレクションピースとしての魅力を高め、所有する喜びを深めます。 このカップは、著名なデザイナーの作品であることから、時と共に価値が増す可能性のある「投資」としての側面と、日常使いを通じて「心地よい体験を提供する」という側面の両方を持ち合わせています。 推奨される使用シーン: • 日常使いの器として: コンパクトなサイズは、エスプレッソや日本茶の湯呑みとして最適です。**日本酒の杯(お猪口)**としても、その温かみのある質感と安定したフォルムが、特別なひとときを演出します。また、小鉢として和え物やデザートを盛り付けたり、ヨーグルトカップとしても活躍します。ストーンウェアは保温性に優れているため、温かい飲み物や料理にも適しており、日々の食卓に北欧の温かみを加えます。 • インテリアのアクセントとして: 小さな花を飾る一輪挿しとして、あるいはアクセサリーや鍵を置く小物入れとして、空間に彩りを添えます。単体でオブジェとして飾るだけでも、その洗練されたフォルムと質感は、リビングや書斎に静かな美意識と温かみを加えるでしょう。 • 特別なギフトとして: デザインやアート、北欧ヴィンテージを愛する方への、心に残る特別な贈り物としても最適です。その希少性と物語は、受け取った方に深い感動を与えることでしょう。 長くご愛用いただくためには、手洗いを推奨いたします。ストーンウェアの釉薬の表情を損なわないよう、優しくお取り扱いください。
-

グンナー・ニールンド作 ロールストランド 1960年製 禾目天目 青釉 おちょこ
¥50
SOLD OUT
1. 序章:北欧と東洋の美の邂逅 本作品は、20世紀半ばのスカンジナビア・モダニズムの革新的な精神と、東アジアの古くから尊ばれる陶磁器の伝統がシームレスに融合した、稀有で魅力的な芸術的対話の証です。スウェーデンの名門ロールストランド社のためにグンナー・ニールンドが制作したこの逸品は、その卓越したデザインと、極めて珍しい鮮やかな青色で表現された「禾目天目」釉薬が特徴です。天目釉の概念は中国の建窯に起源を持ち、日本では非常に重要な文化的価値を持つとされています。一方、グンナー・ニールンドはスウェーデンを代表する著名なデザイナーであり、ロールストランド社はヨーロッパで2番目に古い歴史を持つ由緒ある窯元です。このおちょこは単なる実用的な器に留まらず、芸術的な国境を越えた交流と大胆な創造性を物語る、収集価値の高い美術品です。著名なスウェーデンのモダニズムデザイナー(ニールンド)と製造元(ロールストランド)が、古くから伝わる東アジアの特定の釉薬(天目)を組み合わせたことは、文化間の融合を明確に示唆しています。天目釉は中国と日本の陶磁器史に深く根ざしていますが、1960年代にスカンジナビアの芸術家によってその技法が用いられたことは、意図的な芸術的選択と、これらの美学を再解釈し統合しようとする試みがあったことを示しています。この融合は、単なる装飾品を超え、国際的な芸術的対話の重要な遺物として作品の価値を高めており、現代のデザイナーがいかに多様な世界的伝統から着想を得ていたかを示唆しています。 2. グンナー・ニールンド:北欧陶芸界の革新者 グンナー・ニールンド(1904-1997)は、20世紀の陶芸界において最も著名な人物の一人として広く認識されています 3。パリでフィンランド系スウェーデン人の彫刻家である父と、デンマーク人の陶芸家である母の間に生まれたニールンドは 3、ヘルシンキでの初期の訓練とコペンハーゲンでの建築学の学習を通じて、彼の画期的な陶芸革新のための独自の強固な基盤を築きました。 彼のキャリアにおいて最も重要な時期は、1931年から1958年または1959年までロールストランド社の芸術監督を務めた期間です。この間、ニールンドは「ロールストランドをモダニズムへと導き」、「創造的な責任者でありデザインリーダー」として、同社の美的方向性を形成する上で中心的な役割を果たしました。彼のリーダーシップは、ヨーロッパで最も歴史があり、権威ある陶磁器メーカーの一つであるロールストランド社の作品に多大な影響を与えました。 ニールンドの作品は、「モダンなフォルム」と「マットな長石釉」の卓越した技術によって特徴づけられます。彼は常に「新しいフォルム、素材、釉薬、装飾を試したい」という飽くなき探求心を持っていたことで知られています。この実験的な姿勢は、彼が天目釉のような複雑で反応性の高い釉薬を採用し、革新的な再解釈を行った背景を形成しています。彼の作品は、現在「引っ張りだこ」、「世界中のコレクターが追い求めて止まない」 と評されるほど、世界中のコレクターから高い評価を受けています。 本作品が制作された1960年は、ニールンドの継続的な多作で影響力のある活動期間に当たります。彼は1959年に芸術監督の職を終えた後も、1960年代を通じてDomino、Ritzi、Zenitといった注目すべきシリーズをデザインし、活発に活動を続けました。このおちょこは、彼が釉薬とフォルムの探求を継続していたことを示すものであり、彼の芸術的な活力と陶芸の限界を押し広げようとする揺るぎない姿勢を実証しています。 3. 禾目天目釉:深淵なる青の輝き 「天目」釉薬の伝統は、中国の南宋時代(1127-1279年)に建窯で制作された建盞に起源を持つ豊かな歴史を誇ります。その名は、これらの特徴的な鉄釉の碗が茶の湯に用いられた天目山(天目)の寺院に由来します。これらの碗は、鎌倉時代から室町時代にかけて日本に伝来すると、その独自の釉薬効果と哲学的魅力から、曜変、油滴、禾目といった尊ばれる種類に細かく分類され、非常に高い評価を受けました。 「禾目」(のぎめ)という名称は、文字通り「稲穂の芒(のぎ)」や「兎の毛」を意味し、釉薬表面に現れる繊細な筋状の模様を的確に表現しています。この魅惑的な模様は、通常1230~1250℃の高温で還元焼成される際に、釉薬中の鉄分が結晶化し、流下することによって形成されます。焼成中の釉薬の加熱・冷却サイクルにおける固有の変動性や「窯変」と呼ばれる偶発性により、一つとして同じものがない、唯一無二の作品が生まれます。 伝統的な禾目天目釉が、豊かな茶色、黒、または赤茶色を主とする中で、本作品に見られる深みのある青色は極めて異例です。禾目天目には青藍色や青灰色といった稀なバリエーションが存在することが文献で示されていますが、本作品の鮮やかな光沢は特に目を引きます。この魅惑的な青は、単なる顔料ではなく、「ナマコ青」とも呼ばれる複雑な「物理的な現象」 です。これは、釉薬中に微細な酸化鉄粒子が懸濁し、光線との精密な相互作用によって青色に発光することで生じます。この現象は、釉薬の化学的組成と焼成条件に対するニールンドの高度な理解と制御がなければ、このような稀有で鮮やかな効果を意図的に生み出すことは困難であったことを示唆しています。 この青い禾目天目釉の採用は、ニールンドの作品群において極めて重要な意味を持ちます。彼の釉薬に対する実験的なアプローチや、ロールストランドでの制作において多様な青色を頻繁に取り入れていたことは、彼がこの古代の技法を意図的に、そして見事に再解釈したことを示唆しています。さらに、ロールストランド社のカール=ハリー・スタールハンやグスタフスベリ社のスティグ・リンドベリなど、他の著名なスカンジナビアのデザイナーも「日本の天目釉」を探求し、使用していたことが確認されています。この事実は、天目釉の採用がスカンジナビアの現代陶磁器における広範で意識的な芸術的潮流の一部であったことを示しており、ニールンドの東洋と西洋の革新的な融合を裏付けています。したがって、本作品は、ニールンドが伝統的な東アジアの技法に、明確に現代的で北欧的な感性を吹き込み、陶芸の境界を押し広げた証として存在しています。 4. 作品の細部:画像から読み解く美 本おちょこの最も際立った特徴は、その内側を支配する深く、輝くような青い釉薬です。この魅惑的な色合いは、外縁の豊かでほとんど墨のような紺色から、中心に向かうにつれて明るく、この世のものとは思えないようなスカイブルーへと変化し、深遠な奥行きと宇宙的な魅力を生み出しています。表面は高い光沢を放ち、周囲の光を驚くほど強く反射し、液体のような外観を際立たせ、触覚的な探求を誘います。 青い広がりの中に繊細に織り込まれているのは、中心から優雅に放射状に広がる細い毛のような筋です。これは「禾目」(兎の毛)模様の典型的な特徴です。これらの微妙な線は、濃淡が異なり、光を捉えることで玉虫色の輝きを放ち、まるで光のきらめく糸や兎の毛の繊細な質感を思わせます。これらの筋の精密さと自然な流れは、焼成中の釉薬の挙動に対する卓越した制御を示しています。 碗のまさに中心部では、釉薬が溜まって劇的に明るくなり、明確で輝くような白または淡い青の「眼」を形成しています。この中心の焦点は見る者の視線を内側に引き込み、無限の奥行きの錯覚を生み出し、作品に天体的で、ほとんど瞑想的な質を与えています。これは放射状の模様の視覚的な中心点として機能しています。この深遠な青、放射状の筋、そして輝く中心の「眼」の相互作用は、強い「宇宙的」または「天体的」な美学を創り出しています。この視覚効果は、天目(Tenmoku)の語源である「天の目」(Heaven's Eye)を微妙に反映しており 1、機能的な器を瞑想的な芸術作品へと昇華させ、鑑賞を促します。 おちょこ自体は、直径約7cm、高さ約2.2cmと正確に計測された、完璧にバランスの取れた優雅なフォルムを持っています。わずかに円錐形を帯びたその形状は、伝統的な天目茶碗によく見られる特徴であり 1、快適で安定した持ち心地を保証します。縁の部分は、焼成中に釉薬が重力によって薄くなる傾向があるため、微妙な変化を見せており、本格的な天目作品の釉薬の流れに特徴的な、暖かみのあるわずかに茶色がかった色調が現れている可能性があります 15。 天目釉の固有の性質に忠実に、このおちょこの外観は静的ではありません。その美しさは、光の条件や見る角度によって劇的に変化します 13。青色は深まったり明るくなったりし、「禾目」の筋はより際立ったり、微妙に変化したりすることで、継続的な視覚的発見と、見る者にとって魅力的でインタラクティブな体験を提供します。この作品の美しさは固定されたものではなく、ダイナミックで相互作用的です。釉薬が様々な光の条件や見る角度に反応する様子は 13、所有者が物理的に作品と関わること、すなわち、手に取り、回し、その微妙な変化を観察することを促します。これにより、触覚的および体験的な価値が高まり、より個人的で魅力的な芸術作品となっています。 5. コレクターズアイテムとしての価値と用途 本おちょこは、芸術的な熟練と文化的な融合が交差する、極めて稀な発見です。グンナー・ニールンドがロールストランド社のために制作した作品は、世界中のコレクターから「引っ張りだこ」、「世界中のコレクターが追い求めて止まない」と評されるほど、非常に高く評価されています。伝統的な色合いから逸脱した稀少な青い禾目天目釉が加わることで、その独自性と収集価値は著しく高まり、ニールンドの広範な作品群の中でも際立った存在となっています。 この作品は、ニールンドの開拓者精神と多様な美的影響への受容を示す説得力のある証であり、スカンジナビア・モダニズムと東アジアの古代陶磁器の伝統との間の隔たりを見事に埋めています。単なる美しいオブジェではなく、20世紀半ばの進化するグローバルな芸術風景を体現する歴史的遺物であり、異文化間のインスピレーションと革新の時代を反映しています。ニールンドがコレクターの間で高い評価を得ているデザイナーであるという事実は、すでにその作品の価値を示しています。この作品の価値は多面的であり、物質的な価値を超えて、20世紀の進化するグローバルな芸術風景を反映する文化的遺物としての役割を包含しています。この点が、伝統的なスカンジナビアデザイン愛好家から東アジア陶磁器の愛好家、さらには異文化間の芸術的対話に関心を持つ人々まで、幅広いコレクター層にアピールする要因となっています。天目釉、特に稀少な青色とのユニークな組み合わせは、彼の多様な作品群の中でも際立っており、天目自体が歴史的に珍重されてきたこと 1、そして他のロールストランドのデザイナーも天目釉を探求していたことが、この融合の正当性を裏付けています。この組み合わせは、複数の収集分野に訴求するため、全体的な市場需要と長期的な価値を高めます。 ニールンドの不朽の遺産、スウェーデンで最も著名な陶磁器デザイナーの一人としての地位、そしてユニークな異文化デザイン作品への評価の高まりを考慮すると、この稀少なおちょこは、目の肥えたコレクターにとって強力な投資の可能性を秘めています。その希少性と独特の美学は、ヴィンテージ美術市場におけるその魅力を保証します。 「おちょこ」として完璧なサイズと形状を持ち、「酒器としてはとても贅沢な一品」と評されるように、その深遠な美的魅力は、理想的なディスプレイオブジェとしても機能します。どんなコレクションにおいても魅力的な会話の種となり、貴重な小物を入れる器として、あるいは単に日常の瞑想的な美の源として、その鑑賞には多様性があります。おちょことしての機能性と、魅惑的なディスプレイピースとしての二重の性質は、その多用途性と幅広い層への魅力をさらに高めています。 6. 商品情報 デザイナー (Designer) グンナー・ニールンド (Gunnar Nylund) 製造元 (Manufacturer) ロールストランド (Rörstrand) 製造年 (Year of Production) 1960年 シリーズ/釉薬 (Series/Glaze) 禾目天目 青釉 (Nogime Tenmoku Blue Glaze) 種類 (Type) おちょこ (Sake Cup) 寸法 (Dimensions) 直径 約7cm, 高さ 約2.2cm 素材 (Material) ストーンストーンウェア (Stoneware) 状態 (Condition) 良好なヴィンテージコンディション (Excellent vintage condition) ロールストランド社のグンナー・ニールンドの1960年の禾目天目のおちょこです。直径7㎝、高さ2.2㎝。 ■国:スウェーデン ■会社:ロールストランド ■デザイン:グンナー・ニールンド ■年代:約1960年 ■サイズ:約 Φ7cm 高さ2.2cm ■素材:炻器、禾目天目 ■状態:
-

グンナー・ニールンド作 ロールストランド 1960年製 禾目天目 青釉 小さな花瓶
¥50
SOLD OUT
1. 序章:北欧と東洋の美の融合 本作品は、20世紀半ばのスカンジナビア・モダニズムの革新的な精神と、東アジアの古くから尊ばれる陶磁器の伝統がシームレスに融合した、稀有で魅力的な芸術的対話の証です。スウェーデンの名門ロールストランド社のためにグンナー・ニールンドが制作したこの逸品は、その卓越したデザインと、極めて珍しい鮮やかな青色で表現された「禾目天目」釉薬が特徴です。天目釉の概念は中国の建窯に起源を持ち、日本では非常に重要な文化的価値を持つとされています。一方、グンナー・ニールンドはスウェーデンを代表する著名なデザイナーであり、ロールストランド社はヨーロッパで2番目に古い歴史を持つ由緒ある窯元です。この小さな花瓶は単なる実用的な器に留まらず、芸術的な国境を越えた交流と大胆な創造性を物語る、収集価値の高い美術品です。著名なスウェーデンのモダニズムデザイナー(ニールンド)と製造元(ロールストランド)が、古くから伝わる東アジアの特定の釉薬(天目)を組み合わせたことは、文化間の融合を明確に示唆しています。天目釉は中国と日本の陶磁器史に深く根ざしていますが 、1960年代にスカンジナビアの芸術家によってその技法が用いられたことは、意図的な芸術的選択と、これらの美学を再解釈し統合しようとする試みがあったことを示しています。この融合は、単なる装飾品を超え、国際的な芸術的対話の重要な遺物として作品の価値を高めており、現代のデザイナーがいかに多様な世界的伝統から着想を得ていたかを示唆しています。 2. グンナー・ニールンド:北欧陶芸界の革新者 グンナー・ニールンド(1904-1997)は、20世紀の陶芸界において最も著名な人物の一人として広く認識されています。パリでフィンランド系スウェーデン人の彫刻家である父と、デンマーク人の陶芸家である母の間に生まれたニールンドは 、ヘルシンキでの初期の訓練とコペンハーゲンでの建築学の学習を通じて、彼の画期的な陶芸革新のための独自の強固な基盤を築きました 。彼のキャリアにおいて最も重要な時期は、1931年から1958年または1959年までロールストランド社の芸術監督を務めた期間です。この間、ニールンドは「ロールストランドをモダニズムへと導き」、「創造的な責任者でありデザインリーダー」として、同社の美的方向性を形成する上で中心的な役割を果たしました。彼のリーダーシップは、ヨーロッパで最も歴史があり、権威ある陶磁器メーカーの一つであるロールストランド社の作品に多大な影響を与えました。ニールンドの作品は、「モダンなフォルム」と「マットな長石釉」の卓越した技術によって特徴づけられます。彼は常に「新しいフォルム、素材、釉薬、装飾を試したい」という飽くなき探求心を持っていたことで知られています。この実験的な姿勢は、彼が天目釉のような複雑で反応性の高い釉薬を採用し、革新的な再解釈を行った背景を形成しています。彼の作品は、現在「引っ張りだこ」、「世界中のコレクターが追い求めて止まない」と評されるほど、世界中のコレクターから高い評価を受けています。本作品が制作された1960年は、ニールンドの継続的な多作で影響力のある活動期間に当たります。彼は1959年に芸術監督の職を終えた後も、1960年代を通じてDomino、Ritzi、Zenitといった注目すべきシリーズをデザインし、活発に活動を続けました。この花瓶は、彼が釉薬とフォルムの探求を継続していたことを示すものであり、彼の芸術的な活力と陶芸の限界を押し広げようとする揺るぎない姿勢を実証しています。 3. 禾目天目釉:深淵なる青の輝き 「天目」釉薬の伝統は、中国の南宋時代(1127-1279年)に建窯で制作された建盞に起源を持つ豊かな歴史を誇ります。その名は、これらの特徴的な鉄釉の碗が茶の湯に用いられた天目山(天目)の寺院に由来します。これらの碗は、鎌倉時代から室町時代にかけて日本に伝来すると、その独自の釉薬効果と哲学的魅力から、曜変、油滴、禾目といった尊ばれる種類に細かく分類され、非常に高い評価を受けました。「禾目」(のぎめ)という名称は、文字通り「稲穂の芒(のぎ)」や「兎の毛」を意味し、釉薬表面に現れる繊細な筋状の模様を的確に表現しています。この魅惑的な模様は、通常1230~1250℃の高温で還元焼成される際に、釉薬中の鉄分が結晶化し、流下することによって形成されます。焼成中の釉薬の加熱・冷却サイクルにおける固有の変動性や「窯変」と呼ばれる偶発性により、一つとして同じものがない、唯一無二の作品が生まれます。伝統的な禾目天目釉が、豊かな茶色、黒、または赤茶色を主とする中で、本作品に見られる深みのある青色は極めて異例です。禾目天目には青藍色や青灰色といった稀なバリエーションが存在することが文献で示されていますが 、本作品の鮮やかな光沢は特に目を引きます。この魅惑的な青は、単なる顔料ではなく、「ナマコ青」とも呼ばれる複雑な「物理的な現象」です。これは、釉薬中に微細な酸化鉄粒子が懸濁し、光線との精密な相互作用によって青色に発光することで生じます。この現象は、釉薬の化学的組成と焼成条件に対するニールンドの高度な理解と制御がなければ、このような稀有で鮮やかな効果を意図的に生み出すことは困難であったことを示唆しています。この青い禾目天目釉の採用は、ニールンドの作品群において極めて重要な意味を持ちます。彼の釉薬に対する実験的なアプローチや、ロールストランドでの制作において多様な青色を頻繁に取り入れていたことは、彼がこの古代の技法を意図的に、そして見事に再解釈したことを示唆しています。さらに、ロールストランド社のカール=ハリー・スタールハン やグスタフスベリ社のスティグ・リンドベリ など、他の著名なスカンジナビアのデザイナーも「日本の天目釉」を探求し、使用していたことが確認されています。この事実は、天目釉の採用がスカンジナビアの現代陶磁器における広範で意識的な芸術的潮流の一部であったことを示しており、ニールンドの東洋と西洋の革新的な融合を裏付けています。したがって、本作品は、ニールンドが伝統的な東アジアの技法に、明確に現代的で北欧的な感性を吹き込み、陶芸の境界を押し広げた証として存在しています。 4.作品の細部:画像から読み解く美本花瓶の最も際立った特徴は、その表面を覆う深く、輝くような青い禾目天目釉です。この魅惑的な色合いは、上部の濃い紺色から、胴体部分の鮮やかなコバルトブルーへと変化し、深遠な奥行きと宇宙的な魅力を生み出しています。表面は高い光沢を放ち、周囲の光を驚くほど強く反射し、液体のような外観を際立たせ、触覚的な探求を誘います。青い広がりの中に繊細に織り込まれているのは、釉薬の流下によって形成された、細い毛のような筋です。これは「禾目」(兎の毛)模様の典型的な特徴であり、光を捉えることで玉虫色の輝きを放ち、まるで光のきらめく糸や兎の毛の繊細な質感を思わせます。これらの筋の精密さと自然な流れは、焼成中の釉薬の挙動に対する卓越した制御を示しています。花瓶自体は、底面直径約3.2cm、高さ10.3cm、口部分直径約1.7cmと、小ぶりながらも完璧にバランスの取れた優雅なフォルムを持っています。細く伸びた首と、安定感のある胴体が特徴で、一輪挿しとして、あるいは単体でオブジェとして飾るのに理想的です。天目釉の固有の性質に忠実に、この花瓶の外観は静的ではありません。その美しさは、光の条件や見る角度によって劇的に変化します。青色は深まったり明るくなったりし、「禾目」の筋はより際立ったり、微妙に変化したりすることで、継続的な視覚的発見と、見る者にとって魅力的でインタラクティブな体験を提供します。この作品の美しさは固定されたものではなく、ダイナミックで相互作用的です。釉薬が様々な光の条件や見る角度に反応する様子は、所有者が物理的に作品と関わること、すなわち、手に取り、回し、その微妙な変化を観察することを促します。これにより、触覚的および体験的な価値が高まり、より個人的で魅力的な芸術作品となっています。 5. コレクターズアイテムとしての価値と用途本花瓶は、芸術的な熟練と文化的な融合が交差する、極めて稀な発見です。グンナー・ニールンドがロールストランド社のために制作した作品は、世界中のコレクターから「引っ張りだこ」、「世界中のコレクターが追い求めて止まない」 7 と評されるほど、非常に高く評価されています。伝統的な色合いから逸脱した稀少な青い禾目天目釉が加わることで、その独自性と収集価値は著しく高まり、ニールンドの広範な作品群の中でも際立った存在となっています。この作品は、ニールンドの開拓者精神と多様な美的影響への受容を示す説得力のある証であり、スカンジナビア・モダニズムと東アジアの古代陶磁器の伝統との間の隔たりを見事に埋めています。単なる美しいオブジェではなく、20世紀半ばの進化するグローバルな芸術風景を体現する歴史的遺物であり、異文化間のインスピレーションと革新の時代を反映しています。ニールンドがコレクターの間で高い評価を得ているデザイナーであるという事実は、すでにその作品の価値を示しています。この作品の価値は多面的であり、物質的な価値を超えて、20世紀の進化するグローバルな芸術風景を反映する文化的遺物としての役割を包含しています。この点が、伝統的なスカンジナビアデザイン愛好家から東アジア陶磁器の愛好家、さらには異文化間の芸術的対話に関心を持つ人々まで、幅広いコレクター層にアピールする要因となっています。天目釉、特に稀少な青色とのユニークな組み合わせは、彼の多様な作品群の中でも際立っており、天目自体が歴史的に珍重されてきたこと、そして他のロールストランドのデザイナーも天目釉を探求していたことが、この融合の正当性を裏付けています。この組み合わせは、複数の収集分野に訴求するため、全体的な市場需要と長期的な価値を高めます。ニールンドの不朽の遺産、スウェーデンで最も著名な陶磁器デザイナーの一人としての地位、そしてユニークな異文化デザイン作品への評価の高まりを考慮すると、この稀少な花瓶は、目の肥えたコレクターにとって強力な投資の可能性を秘めています。その希少性と独特の美学は、ヴィンテージ美術市場におけるその魅力を保証します。小さな花瓶として、一輪の花を飾るのに最適であり、その深遠な美的魅力は、理想的なディスプレイオブジェとしても機能します。どんなコレクションにおいても魅力的な会話の種となり、貴重な小物を入れる器として、あるいは単に日常の瞑想的な美の源として、その鑑賞には多様性があります。 商品情報項目 国 (Country)スウェーデン (Sweden) 会社 (Company)ロールストランド (Rörstrand) デザイン (Designer)グンナー・ニールンド (Gunnar Nylund) 年代 (Year of Production)約1960年 シリーズ/釉薬 (Series/Glaze)禾目天目 青釉 (Nogime Tenmoku Blue Glaze) 種類 (Type)花瓶 (Vase) 寸法 (Dimensions)底面Φ約3.2cm, 高さ10.3cm, 口部分Φ約1.7cm 素材 (Material)ストーンウェア (Stoneware)・禾目天目 状態 (Condition)良好なヴィンテージコンディション (Excellent vintage condition)
-

木のモルタル、アフリカ
¥50
SOLD OUT
■産地:アフリカ大陸 ■サイズ:約 高 19cm 上Φ19.5cm 底面Φ15cm ■素材:木 ■状態:ひびあり
-

スウェーデン、19世紀の木製ボウル
¥50
SOLD OUT
長い年月を経た美しい風合いが魅力の、19世紀スウェーデン製の木製ボウルをご紹介いたします。 北欧の暮らしに根付いた手仕事の温もり 約14.6~15cmの直径と、5.7~5.9cmの高さを持つこの木製ボウルは、使い込まれたパティーナ(古色)が、その長い歴史と時を超えた魅力を物語っています。 職人の手仕事が息づく逸品 足踏み式のろくろを用いて、熟練の職人が一つひとつ丁寧に作り上げたこのボウルは、大量生産では決して生み出せない、温かみと手仕事ならではの味わいに溢れています。 古き良き時代の息吹を感じる一品 北欧の古民藝ならではの素朴さと、時を経た木の質感は、現代の暮らしにも自然と溶け込み、空間に落ち着きと安らぎをもたらします。 ■国:スウェーデン ■年代:19世紀 ■サイズ:約 Φ14.6-15㎝ 高さ5.7-5.9㎝ ■素材:ヨーロパブナ ■状態:
-

【希少なスウェーデンアンティーク】19世紀 異素材組み合わせの木箱 - 旋盤製ベースとベントウッド製蓋 (スウェープアスク)
¥50
SOLD OUT
19世紀のスウェーデンより届いた、少し変わった、しかし非常に魅力的な木箱をご紹介します。北欧の伝統的な木工技術が組み合わさった、他に類を見ない一品です。 歴史と技術の融合 この木箱の下の部分は、古くから伝わる足踏み轆轤(ろくろ)によって作られた、見事な円形の旋盤細工です。対照的に、蓋の部分はスウェーデンに古くから伝わる伝統技術である「スウェープアスク(Svepask)」の技法(ベントウッド、曲げ木)を用いて作られています。 スウェープアスクの技法とは、薄く割いた木材を、温水で柔らかくしたり蒸したり(Basning - バスニング)して 柔軟な状態にし、円形や楕円形に曲げ加工するものです。その両端を重ね合わせ、根の繊維や木の釘などで固定して容器の胴体や蓋を作ります。スウェープアスクは、バターや衣類、個人的な持ち物など、様々なものを収納するための日用品としてスウェーデンの各地で作られていました。 この木箱の場合、元々の木箱の蓋(おそらくベースと同様の旋盤製)が壊れてしまったのでしょう。そこに、当時の職人が身近で一般的だったスウェープアスクの技術を用い、代替の蓋を製作したと考えられます。これにより、一つの箱に異なる時代の必要性や技術が共存する、独特な風合いと歴史が刻まれました。 特徴 特筆すべきは、旋盤製の下部とスウェープアスク製の蓋、どちらの内側にも類似した美しい赤色の彩色が施されている点です(※内側の赤色に関する情報は、提供された歴史資料には記載されておらず、本品の固有の特徴です)。この赤色は、かつてこの箱が大切に使われ、彩られていた名残かもしれません。 サイズは、旋盤製の下部が直径約8.5cm、そしてスウェープアスク製の蓋は直径約9.7cmです。全体高さは約4.9cmで、直径7cm、高さ3cm程度の小ぶりな物、例えば小さな「おちょこ」などを収めるのにちょうど良いサイズ感です。スウェープアスクは、個人の所有物や裁縫道具などを入れるためのシンプルな入れ物としても使われていました。 異なる技術と歴史が織りなすこの木箱は、単なる古い道具ではなく、使い手の工夫や職人の技術、そして時代の流れを感じさせる、ストーリーのある北欧古民藝品です。アンティークやフォークアートのコレクションに、またお部屋のディスプレイに、特別な存在感を添えるでしょう。 商品詳細 •国: スウェーデン •年代: 19世紀 •サイズ: 約 Φ9.7㎝ (蓋の直径) 高さ4.9cm •素材: 木材 •状態: [アンティーク品としての状態を記載 - 例:時代の使用感や傷が見られますが、構造的な問題はなく、アンティーク品として良い状態です。画像をよくご確認ください。]
-

18-19世紀スウェーデンの木のボウル。
¥50
SOLD OUT
スウェーデンの18-19世紀の足踏み轆轤で作られた木のボウルです。 ■国:スウェーデン ■年代:18-19世紀 ■サイズ:約 Φ23.3-23.6cm 高さ6.5-7cm ■素材:ヨーロパブナ ■状態:
-

【北欧アンティーク】スウェーデン 18-19世紀 轆轤挽き木製皿
¥50
SOLD OUT
スウェーデンの豊かな自然の中で育まれ、長い歴史を静かに見守ってきた素朴な木工品をご紹介します。こちらは18世紀から19世紀にかけて、北欧の家庭で日々の暮らしに寄り添ってきた、アンティークの木製皿です。 伝統の技と素材の魅力 この皿は、当時の熟練の職人が、木材から丁寧に轆轤を用いて挽き上げた逸品です。機械にはない、手仕事ならではの温かみ と、木材が持つ自然な木目や表情が最大限に活かされています。素材としては、当時の木製皿や箱に広く用いられた、ヨーロパブナ材が考えられます。ヨーロパブナは密度が高く丈夫で、食材の風味を損なわない特性を持つため、古くから食器や容器の材料として重宝されました。 暮らしに深く根差した歴史と背景 木製の皿やボウルは、18世紀頃からスウェーデンの農民の間で一般的になった日常の道具です 。特にスウェーデン南西部のセーハラッドスビーグデン地方(Sjuhäradsbygden)は、古くから木工品の製造が盛んな地域でした。この地域の農民兼行商人「skålaknallarna(スコーラカナラルナ)」は、17世紀から19世紀半ばにかけて、挽き物の皿や箱などを大量に製造し、スウェーデン各地や近隣国に運んで販売することで、これらの木製食器を広く普及させました。記録によると、1771年だけで78,030枚もの木製皿が運ばれたとされます。 当時の農家では、19世紀後半まで お粥,や汁物などの普段の食事を、大きな共同の鉢から家族や共同体で直接食べる習慣が一般的でした。個人の皿は所有していても、日常的には使われず、特別な機会(gillen)にのみ使用されることもありました。 この皿のサイズ、直径約24cmから24.5cmは、当時の一般的な個人の木製皿の直径(19-20cm)よりもやや大きく、盛り付け用の平皿(約28cm)に近いサイズです。これは、単なる個人の食事用としてだけでなく、家族や客人との食事の際に料理を盛り付けたり、あるいはより大きな 共同の鉢を補完する取り皿としてなど、当時の多様な食習慣の中で実用的な器として、人々の営みを見守ってきた歴史を物語っています。 年月を物語る風合いとパティナ この皿は長い年月を経て、使い込まれた道具だけが持つ独特の深い色合いと風合い、そしてパティナ(古艶)を纏っています。表面には、長年の使用による細かな傷や擦れ、シミ、摩耗が見られますが、それこそが本物のアンティークである証であり、唯一無二の魅力となっています。現代の基準では「良い状態」に分類される、アンティークとして自然な状態です。均一でない木目や、手挽きによるわずかな歪みも、工業製品にはない手仕事ならではの素朴な美しさを引き立てています。 現代の空間に新たな物語を 北欧の素朴な民藝品として、現代の空間に温かみを添えるディスプレイに。お気に入りの雑貨を飾るトレーとしても素敵です。一枚の皿に深く刻まれた、過ぎ去りし時代の暮らしの物語を感じて、あなたの日常に新たな彩りを加えてみませんか。 • 国: スウェーデン • 年代: 18-19世紀 • サイズ: 約 直径24cm~24.5cm • 素材: 木製(ヨーロパブナ材) • 状態: 経年による傷、シミ、摩耗、木材の自然な収縮による歪みなどが見られますが、アンティークならではの風合いとしてお楽しみいただけます。
-

【北欧アンティーク民藝】スウェーデン 19世紀 スヴェープアスク(曲げ木箱) - 時を超えた黒
¥50
SOLD OUT
北欧、特にスウェーデンの素朴な暮らしの中で長く愛用されてきた伝統的な木工品、スヴェープアスク (svepask) をご紹介します。これらのユニークな曲げ木製の容器は、スウェーデンの田舎で人々の日常生活に不可欠な道具であり、伝統的な スロイド (slöjd) すなわち手工芸 の精神と創意工夫を体現しています。 この特定のスヴェープアスクは19世紀に製作されたものと考えられます。元々は木材本来の風合いを活かした仕上げだったと考えられますが、おそらく20世紀初頭に深い漆黒に塗り替えられました。これは当時の家庭で流行した美意識や、特定の用途への適応を反映しているのかもしれません。 手仕事ならではの完全に均一ではない形、円形でありながらもわずかに揺らぎのある形状が、大量生産品にはない温かみと個性を与えています。サイズは円周が約17.6cmから18cm、高さが約10cmです。使い込まれて擦れた漆黒の表面からは、下地の木材の色がわずかに覗き、独特のパティナ(古艶)と奥行きのある表情を生み出しています。このような本物の使い込みによる風合いは、アンティークの民芸品において高く評価されます。 この小さな箱は、単に日用品を収めるだけでなく、空間に静かな存在感を放ちます。北欧の厳しい自然と人々の暮らしの中で育まれた 民藝 (folk art) の精神を感じさせる、唯一無二のディスプレイアイテムとなるでしょう。 商品詳細 • 国: スウェーデン • 年代: 19世紀(黒塗装はおそらく20世紀初頭頃) • サイズ: 円周 約17.6~18cm, 高さ 約10cm • 素材: 木製 • 状態: 経年による傷、シミ、塗装の剥がれが見られます [以前の説明]。完璧な円形ではありません [以前の説明]。オリジナルの木の釘はごくわずかで、多くは後年施された釘による補修跡があります。これらの状態は、この箱が長く大切に使われてきた歴史と、歴史ある民藝品ならではの風合いとしてお楽しみいただけます。 スヴェープアスクの歴史と製作方法 スヴェープアスクの製作には、スヴェープテクニーク (svepteknik) と呼ばれる伝統技法が用いられます。この技術は非常に古くから行われており、木製のスヴェープケール (svepkärl - 曲げ木製容器) の最も古い確実な例は青銅器時代まで遡り、オーストリアアルプスで発見されています。スウェーデンでは、ヴァイキング時代のスヴェープケールの痕跡が見つかっています。ヴァイキング時代のノルウェーの墳墓からも見つかっています。スウェーデンでは鉄器時代に一般的になり始めました。1400年代以降の絵画にも多く見られます。古代エジプトの墓からも約4000年前の例が見つかっています。この技術は中央ヨーロッパから北欧に広がったと考えられています。 スヴェープテクニークでは、丸太から木の繊維の方向に沿って薄い木片(スパーン spån)を注意深く割る という準備工程が重要です。この準備により、木材は割れることなく曲げることが可能となります。木片の厚さは、容器の大きさによって異なりますが、通常は 約2ミリメートルから12ミリメートル程度 です。使用される木材としては、マツ、カバ、ヤナギ、トウヒなどがあります。カバ材は裂けやすく、無味であるため食品容器に適しています。樹皮に近い外側の木材が使われることもあります。秋から冬にかけて木材を伐採すると、曲げる際に粘りが出るとする回答者もいます。裂く際には、裂きナイフと手を使う方法や、手でスパーンを引き裂く方法などがあります。手斧やバンドナイフ(bandkniv)、スカヴェ(skave)といった手工具も用いられます。 木片はその後、蒸気で柔らかくしたり、お湯に浸けたりして柔軟性が与えられます(この技法は バスニング (basning) と呼ばれます)。これにより木材中のリグニンが軟化します。柔らかくなった木片は、型を使って、あるいはフリーハンドで、望みの円形または楕円形に曲げられます 。膝の上で曲げるフリーハンドの方法もありました。木片の両端を重ね合わせて側壁が作られます 。 側壁の継ぎ目は、かつては根(カバの根、トウヒやネズの根)や、木片自体、腱、あるいは鳥の羽根軸などで縫い合わせられていました [以前の説明, 6, 62, 92]。スウェーデン北部ではチェーンステッチ(kedjesömmar)、南部ではスネールイステッチ(snärjsömmar)が使われることが多かったようです。底板はしばしば木の釘で接合されました。特にスウェーデン北部では、底板に段差を作り、そこに側壁をはめ込んで縫い合わせる技法が見られます。一方、南部では底板を側壁の内側に配置して木の釘で固定することが多かったようです。この特定の箱の側面の継ぎ目には、元々は小さな木の釘で固定されていた痕跡が残っており、後年により頑丈な鉄の釘で丁寧に修繕されています。 スヴェープアスクには様々な種類や形があり、大きさや用途も多様です。日用品や食料品(バター、クネッケブロード、粉、塩など)、衣類や身の回りのものを入れるのに使われました。旅行用の箱(färdskrin)としても使われました。液体を入れても漏れないように作ることも可能でした。サーミの人々にとっては、持ち運びが容易であることから、移動式住居(コタ)における唯一の家具として不可欠なものでした。計量容器(målkärl) や、ふるい(siktar) の枠としても作られました。蓋が箱の外側にかぶさる「スヴェープアスク」の他、蓋が側壁の間に収まりロックできる「エスカ(äska)」、取手付きの籠「スヴェープコルグ(svepkorg)」、大型で金具が付いた「スヴェープスクリン/スヴェープキスタ(svepskrin/svepkista)」 などがありました。「エスカ」はかつて女性のハンドバッグとしても使われたそうです。 装飾は様々で、無装飾のものから、彫刻(karvsnitt)、焼き絵、またはペイントが施されたものまであります。南スウェーデンやノルウェーでは焼き付け装飾が人気でした。中スウェーデンでは彫刻や切り込み、動物モチーフも一般的でした。北スウェーデンでは装飾は控えめでしたが、1700年代からはペイントが人気になりました。アンティーク品には、しばしば ローゼモーリング (Rosemaling - バラの絵付け) と呼ばれる伝統的なペイントが施されています。これは地域によって特徴が異なります。装飾は、全面を埋め尽くしたり、自然のモチーフを様式化したり、象徴的なメッセージを込めたりすることがありました。 現代でもスヴェープテクニークは行われており、機械化された工程もありますが、パン皿や収納容器として機能的な役割を持ち、その美学も現代人に評価されています。中世市場やLARP(ライブアクションロールプレイング)コミュニティからの関心もあり、手で木を裂く伝統技法への注目も再び高まっています。ワークショップやコースも開催されています。
-

伝説の陶芸家 ベルント・フリーベリ作 1968年 グスタフスベリ製 ストーンウェアカップ - 至高のミニチュア芸術作品
¥50
SOLD OUT
スウェーデンを代表する陶芸家、ベルント・フリーベリ (Berndt Friberg, 1899-1981) による、1968年製の稀少なストーンウェアカップをご紹介します。フリーベリの「神の手」と称された卓越したろくろ技術と、繊細かつ官能的なフォルム、そして奥行きのある釉薬の表現が凝縮された、まさに芸術作品です。東洋の美意識に深く影響を受け、京都や東京の国立美術館にも作品が所蔵されている彼の作品は、日本のコレクターにも特別な共感を呼び起こすでしょう。 -------------------------------------------------------------------------------- 商品詳細: • デザイナー: ベルント・フリーベリ (Berndt Friberg) • 製造元: グスタフスベリ (Gustavsberg) • 製造年: 1968年 • 素材: ストーンウェア (Stoneware) 禾目天目 青釉 • 寸法: 直径 8.4cm, 高さ 4.7cm • サイン: Friberg, Gustavsberg Studio Hand, J (1968年を示す文字) •コンディション: 経年によるわずかな使用感はあるものの、全体的に非常に良好なヴィンテージコンディションを保っています。目立つ傷や欠け、修復跡は見られません。 -------------------------------------------------------------------------------- 1. フリーベリの「神の手」が生み出す完璧なフォルムとミニチュアの魅力 このカップは、直径8.4cm、高さ4.7cmという手のひらサイズのミニチュア作品であり、フリーベリの芸術的領域の広さと細部への並外れたこだわりを象徴しています。彼は13歳から陶芸作品を手掛けており、1934年にはグスタフスベリ磁器工場に到着するまでに、Höganäsbolaget、Raus Stenkärlsfabrikなど複数の陶器工場で経験を積んだ熟練の職人でした。彼は、すべての作品を自らの手で一つ一つろくろ成形し、「手投げの完璧主義者」として、自身の厳格な基準に満たないものは容赦なく破棄したことで知られています。その並外れた技術の高さから、陶芸家仲間からは畏敬の念を込めて「神の手 (Hand of God)」と称されました。この小さなカップにも、彼の高度な技術と、一点一点に注がれた情熱が遺憾なく発揮されており、単なる量産品ではない極めて高い基準を満たした芸術作品であることを強く示唆しています。 2. 東洋の美学が息づく繊細な釉薬表現 本作品の釉薬は、淡い色調の中に、繊細な質感と独特の模様が特徴的です。フリーベリは釉薬の化学に精通しており、その配合を詳細に記録した「黒い手帳」を所有していたことでも知られています。彼のセラミック作品は、その精緻なマット釉薬が特徴的で、これらは中国や日本の伝統的な釉薬を念頭に置いて開発されました。特に、彼の代表的な「ハーレムファー(兎の毛)効果」は、釉薬が塗られた部分に繊細な線条(ストリエーション)が現れ、器に見事な奥行きを与えます。 1960年代には「オックスブラッド」や彼のお気に入りだった「アニアラ」といった光沢のある釉薬も主流となりましたが、本作品の釉薬は「半マットで柔らかな光沢」に近い質感で、落ち着いた色合いの中に深みと動きを感じさせます。彼の釉薬は「柔らかく、何層にも重ねられ、しばしば絹のような、あるいはベルベットのような質感」を持つことがあり、このカップの釉薬もその洗練された表現の一例と言えるでしょう。画像から読み取れる斑点状のテクスチャーや口縁部近くの幾何学的な線状パターンは、1957-58年頃から釉薬に様々なパターンを取り入れ始め、1968年製の作品に「ユニークな釉薬パターン」が見られるという記述に合致しています。これは、1960年代においてもフリーベリが釉薬の多様な表現を積極的に追求していたことを示しています。 3. グスタフスベリ工房とフリーベリの芸術的遺産 ベルント・フリーベリは、1934年に名門グスタフスベリ磁器工場 (Gustavsberg porslinsfabrik) に入社し、1944年からはスウェーデンで最も多作で有名な陶芸家の一人であるウィルヘルム・コーゲ (Wilhelm Kåge) とスティグ・リンドベリ (Stig Lindberg) のもとでろくろ師として活躍しました。彼はグスタフスベリ・スタジオ (Gustavsberg Studio) でも活動しました。このスタジオは、1942年にコーゲによって実験的な工房として設立され、工場内にありながらもアーティストに「自由な表現の手段と実験の場」を提供することを目的としていました。フリーベリは、このスタジオで彼の象徴的なフォルムと釉薬を発展させました。グスタフスベリが大規模な工場である一方で、G-スタジオが「自由な表現と実験の場」として設立されたという事実は、フリーベリのような完璧主義のアーティストが、なぜ工業的な環境下でこれほどまでにユニークで芸術性の高いハンドメイド作品を生み出せたのかを明確に説明しています。 フリーベリの作品は、スウェーデン国王グスタフ6世アドルフが100点以上を収集したのをはじめ、ロバート・メイプルソープ (Robert Mapplethorpe) やイヴ・サンローラン (Yves Saint Laurent) といった著名なコレクターにも愛されました。彼の作品は、ストックホルムの国立美術館、コペンハーゲンのデンマーク国立美術館、ニューヨークの近代美術館、メトロポリタン美術館、そして京都や東京の国立美術館を含む世界各地の権威ある公共コレクションに収蔵されています。彼はミラノ・トリエンナーレでの金賞 (1948年, 1951年, 1954年) やファエンツァ国際陶芸コンペティションでの一等賞 (1965年) など、数々の栄誉ある賞を受賞しています。また、1964年にはLO文化賞、1979年にはプリンス・ユージン・メダルも受賞しています。フリーベリは1981年に亡くなるまでグスタフスベリに忠実に働き続けました。 -------------------------------------------------------------------------------- 結論: このベルント・フリーベリ作のストーンウェアカップは、彼の卓越した職人技、完璧主義、そして東洋の美意識への深い敬意が凝縮された、真にユニークな芸術作品です。その小ぶりなサイズは、フリーベリの多様な才能と、細部への揺るぎないこだわりを象徴しており、釉薬に見られる繊細なパターンは、1960年代における彼の革新的な表現の一端を示しています。グスタフスベリのG-スタジオという創造的な環境で生み出されたこの作品は、単なる実用品ではなく、アーティストの自由な精神と高度な技術が融合したアートピースとしての価値を確立しています。日本の美術館にも所蔵され、東洋の美学に深く影響を受けたその様式は、日本のコレクターにとって特別な共感を呼び起こすことでしょう。底部のサインが保証する真正性とともに、このカップは、ベルント・フリーベリの遺産を現代に伝える貴重な逸品であり、あなたのコレクションに深みと洗練をもたらすこと間違いありません。フリーベリの芸術的遺産を現代に伝える、貴重な機会をお見逃しなく。
-

アンティークサンプラーデンマーク1860年
¥50
SOLD OUT
美しい絵柄と繊細な刺繡が施されたアンティークサンプラー。デンマークの農村地帯で1860年に作られたこの一品は、当時の少女たちが手掛けた練習用の布地で、その後100年以上も大切に保管されてきました。 繊細な針仕事と鮮やかな色使いが魅力的で、ヨーロッパのアンティークコレクターの間で高い評価を得ています。 このアンティークサンプラーには、当時の少女たちがひたすらに刺繍に打ち込んだ時間や想いが込められています。この一枚を手にした時、その歴史や物語があなたにも伝わることでしょう。 ■国:デンマーク ■年代:1860年 ■サイズ:約 高 32cm 横 32cm ■素材:布 ■状態:
-

フィリピンの「聖ロクス」(聖ロック)の聖人像。
¥50
SOLD OUT
フィリピンの「聖ロクス」(聖ロック)の聖人像。 犬の守護聖人であり、疫病や流行病に対して祈願される聖人です。 ■国:フィリピン ■年代:19世紀 ■サイズ:約 高さ38㎝ 横幅13.5㎝ 奥行12㎝ ■素材:木製 ■状態:経年によるキズや擦れ、汚れはあります、足欠けあり、手に直し
-

美しいパティナのある18世紀スウェーデンの木皿
¥50
SOLD OUT
時を超えて、暮らしを彩る。18世紀スウェーデン、ヨーロパブナの木皿。 悠久の時を経た、奇跡の出会い。 遥か18世紀、スウェーデンで生まれたヨーロパブナの木の皿。足踏み式のろくろを操り、職人の魂を込めて一つひとつ丁寧に作られた、世界にたった一つの逸品です。 温もりを伝える、手仕事の痕跡。 ヨーロパブナ特有の美しい木目と、長年使い込まれた証である深みのあるパティナ(緑青)が、歴史の重みを物語ります。手仕事ならではの温かみが、現代の暮らしにそっと寄り添います。 暮らしに息づく、美意識。 直径約19cmという手頃なサイズは、日常使いに最適。朝のヨーグルトやサラダ、午後のティータイムのお菓子など、様々なシーンで活躍します。 一点ものとの出会い。 同じものは二つとない、まさに一点もの。あなただけの特別な存在となるでしょう。 アンティークの魅力。 年月を経て、さらに味わいを増したアンティーク。傷や汚れもまた、その歴史を物語る大切な要素です。ご理解いただける方のみ、ご検討ください ■国:スウェーデン ■年代:18世紀 ■サイズ:約 Φ18.5-18.9 ■素材:ヨーロパブナ ■状態:経年によるキズや擦れ、汚れはあります
-

18-19世紀スウェーデンの木皿
¥50
SOLD OUT
時を刻む、温もりと歴史。18-19世紀スウェーデン製ヨーロパブナ材木製プレート 北欧の古民芸、特に18~19世紀のスウェーデンで生まれた木製プレートは、時を超えて私たちの心を惹きつける魅力を持っています。今回ご紹介するのは、ヨーロパブナ材をろくろで丁寧に成形し、長い年月を経てきた温もりと歴史を感じさせる逸品です。 使い込まれた風合いが物語る、暮らしの記憶 明るい色合いのヨーロパブナ材は、使い込まれたことで独特の風合いを醸し出し、表面には当時の暮らしを物語るナイフ跡が刻まれています。それは、単なる傷ではなく、所有者が大切に使い続けてきた証。一つ一つの傷やへこみに、家族の食卓を囲む温かな光景や、日々の暮らしの中で育まれた物語が宿っているかのようです。 ろくろ細工が生み出す、素朴な美しさ ろくろで成形されたプレートは、均整の取れた美しいフォルムが特徴です。手仕事ならではの温かみが感じられる素朴な美しさは、現代の工業製品にはない魅力と言えるでしょう。 北欧の暮らしを、現代の食卓に この木製プレートは、アンティークとして鑑賞するだけでなく、実際に食卓で使うこともおすすめです。パンやチーズを盛り付けたり、お菓子を並べたりするだけで、いつもの食卓が特別な空間に変わります。北欧の暮らしに思いを馳せながら、日々の食卓を豊かに彩ってみませんか? ■国:スウェーデン ■年代:18-19世紀 ■サイズ:約 Φ17.7-18㎝ ■素材:ヨーロパブナ ■状態: